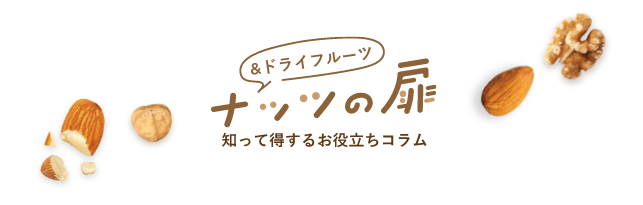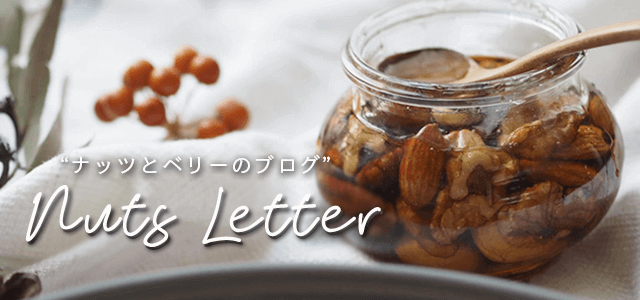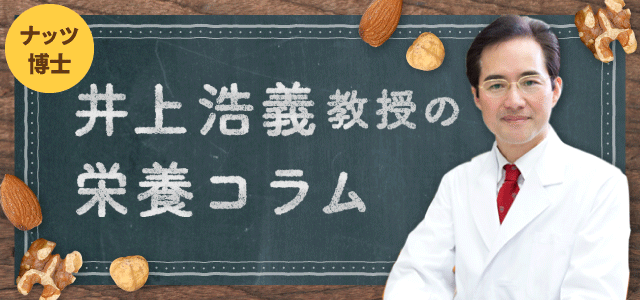ピーナッツはナッツじゃない?ピーナッツの分類や栄養素を解説
「ナッツ」と聞いてピーナッツを思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、厳密に言うとピーナッツはナッツの仲間ではありません。ナッツとピーナッツが異なる種類である理由は、それぞれの定義を知ることで理解できます。
また、ピーナッツはナッツに分類はされないものの、ナッツに負けないほど健康に役立つ食品です。そこで今回は、ピーナッツの特徴やナッツの定義から、ピーナッツの栄養素と食べる際の注意点まで詳しく紹介します。
1. ピーナッツはナッツじゃない?
ピーナッツは名前に「ナッツ」がついているため、ナッツの仲間と考える方も多くいます。しかし、実はピーナッツはナッツの仲間ではありません。これには、ピーナッツが「豆類」に属する一方で、ナッツが「種実類」に属する点が大きく関係します。
そこでまずは、ピーナッツの特徴とナッツの定義について詳しく紹介します。
1-1. ピーナッツとは
ピーナッツとは、マメ科の植物である落花生(ラッカセイ)の実で、「豆類」に分類されます。
落花生の実の見た目はナッツに似ており、乾燥させて煎るとナッツのような香ばしい風味が立つことから、「Pea(豆)」と「nuts(ナッツ)」を組み合わせて「Peanuts(ピーナッツ)」と呼ばれるようになりました。
1-2. ナッツの定義とは
ナッツとは、硬い殻や複数の皮に包まれた木の実や種子の総称で、すべて「種実類」、いわゆる「木の実類」に分類されます。実る植物によって様々な種類があり、種類によって食べられる部位も異なることが特徴です。
例えばナッツの代表的な種類であるアーモンドは、バラ科サクラ属の落葉高木に実る種子で、殻を割った中の「仁」という部分が食用部分となります。
一方で、ウルシ科カシューナット属の常緑高木に実るカシューナッツは「種子」そのものが、カバノキ科ハシバミ属の落葉低木に実るヘーゼルナッツは堅い殻を割ると出てくる「堅果」が食べられる部分となります。
ナッツには、ほかにもクルミやピスタチオ、マカダミアナッツなどの種類があります。(※出典1)
1-3. ピーナッツがナッツと勘違いされる理由は?
前述の通り、ピーナッツは豆類(マメ科)に、ナッツは種実類に分類されるため、厳密に言うとピーナッツはナッツの仲間ではありません。
ピーナッツがナッツと勘違いされやすい理由としては、名前や見た目、食感だけでなく、栄養成分がナッツに近いという点も挙げられます。
豆類の多くは、炭水化物が多い一方で、ナッツは炭水化物が少なく脂質が多く含まれているのが特徴です。その中でピーナッツは、ほかの豆類に比べて炭水化物が少なく、脂質が多いというナッツと似た栄養成分となっています。
また、慣習的にピーナッツもナッツの仲間として扱われることが多くあります。実際に、文部科学省の食品成分表ではナッツと同じ「種実類」としてカテゴリ分けされています。加えて、スーパーやコンビニ、ネット通販などで販売されているミックスナッツの商品にも、ピーナッツが含まれているものが多く見られます。
2. ピーナッツに含まれる栄養素
ピーナッツは、ナッツに近い栄養成分組成となっています。
ここからは、ピーナッツに含まれる様々な栄養素の中でも、特に代表的な「たんぱく質」「不飽和脂肪酸」「ポリフェノール」「ビタミン」について紹介します。
2-1. たんぱく質
たんぱく質とは、アミノ酸が鎖状に多数結合してつくられた高分子化合物で、筋肉や臓器、血液など体のあらゆる組織を構成する重要な栄養素です。
ピーナッツにはたんぱく質が豊富に含まれています。100g中に含まれるたんぱく質の量は肉類よりも多く、たとえば豚肉100g当たりに含まれるたんぱく質が14.4gなのに対し、ピーナッツには25.0gも含まれています。(※出典2)
良質なたんぱく質を日々取り入れることで、筋肉の修復や維持、免疫機能の強化など、健康的な体づくりに役立つでしょう。
2-2. 不飽和脂肪酸
不飽和脂肪酸とは、脂肪を構成する脂肪酸のうち、炭素間に二重結合をもつ脂肪酸を指します。植物や魚の脂に多く含まれることが特徴で、体内で合成できないものもあるので、健康維持・生活習慣病予防のためにも積極的に取り入れたい栄養素です。
不飽和脂肪酸には「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」の2つがあり、ピーナッツには、一価不飽和脂肪酸の中でも特に代表的な「オレイン酸」が含まれています。このオレイン酸は、血液中のコレステロールバランスを整える働きをすることから、健康維持に役立つとされています。(※出典3)
2-3. ポリフェノール
ポリフェノールとは、植物が紫外線や害虫・微生物から身を守るためにつくりだす苦味や色素の天然成分で、強い抗酸化作用をもつことが特徴です。活性酸素をはじめとした有害物質を無害な物質に変える働きによって、動脈硬化などの生活習慣病の予防に役立ちます。
ポリフェノールには「アントシアニン」や「カテキン」、「カカオポリフェノール」などの様々な種類があり、それぞれ期待できる作用も異なります。
ピーナッツの薄皮部分には、ポリフェノールの一種である「レスベラトロール」が含まれています。
2-4. ビタミン
ビタミンとは、人を含む生体の機能を正常に保つために欠かせない有機化合物です。性質によって、「水溶性ビタミン」と「脂溶性ビタミン」の2種類に分けられます。
水溶性ビタミンは、代謝に必要な酵素の働きをサポートする重要な役割を果たしています。水に溶ける性質をもっており、過剰なビタミンは尿として排出されることが特徴です。
脂溶性ビタミンは、身体機能を正常に保つ働きをします。水に溶けない性質をもっているため、過剰摂取には注意が必要です。
ピーナッツには、主に水溶性ビタミンである「ビタミンB1」「ナイアシン(ビタミンB3)」や、脂溶性ビタミンである「ビタミンE」が多く含まれています。
ビタミンB1とナイアシンは、前述の通りエネルギー代謝をサポートする重要な役割を果たします。ビタミンEは「抗酸化ビタミン」とも呼ばれ、体内の細胞を守る働きをします。
3. ピーナッツを食べるときの注意点
ピーナッツはナッツと同様に栄養価が高く、健康維持を目指す方にとってはおすすめの食品です。
しかし、食べれば食べるほどよいというわけではありません。なぜなら、ピーナッツは栄養価が高い分、高カロリーであるためです。健康維持のためにピーナッツを食べる場合は、摂取量をコントロールしましょう。
1日200kcal以内という間食の適量をピーナッツに換算すると「20~30粒程度」が目安になります。このくらいの量であれば、必要な栄養素を補給しつつ、過剰なカロリー摂取を防ぐことができます。
まとめ
ピーナッツは豆類(マメ科)に分類される一方で、ナッツは種実類に分類されます。そのため、ピーナッツはナッツの仲間ではありません。しかし、見た目や栄養成分がナッツに似ていることから、慣習的にピーナッツはナッツの仲間として扱われる傾向にあります。
デルタの「ナッツ屋さん」シリーズおよび「ロカボナッツ」シリーズでは、種実類に分類されるナッツのみを扱っています。健康や美容に気を使っている方、または日々の食事習慣を見直したいと考えている方は、ぜひデルタのナッツをお試しください。
出典一覧
MOVIES 動画
キャンポス ブラザーズ社のサステナビリティ アニメーション動画
デルタの世界のパートナーをご紹介!

 ロカボナッツシリーズ
ロカボナッツシリーズ くだもの屋さん&ナッツ屋さんシリーズ
くだもの屋さん&ナッツ屋さんシリーズ カリフォルニア産フレッシュパック
カリフォルニア産フレッシュパック 生ブルーベリー瓶詰めシリーズ
生ブルーベリー瓶詰めシリーズ 産地パックシリーズ
産地パックシリーズ デルタグルメシリーズ
デルタグルメシリーズ アーモンド
アーモンド クルミ
クルミ マカダミアナッツ
マカダミアナッツ レーズン
レーズン プルーン
プルーン トルコ産・チュニジア産
トルコ産・チュニジア産 トロピカルフルーツ
トロピカルフルーツ ベリー類
ベリー類 ピスタチオ
ピスタチオ その他ナッツ&ドライフルーツ
その他ナッツ&ドライフルーツ 日本国産ドライフルーツ
日本国産ドライフルーツ